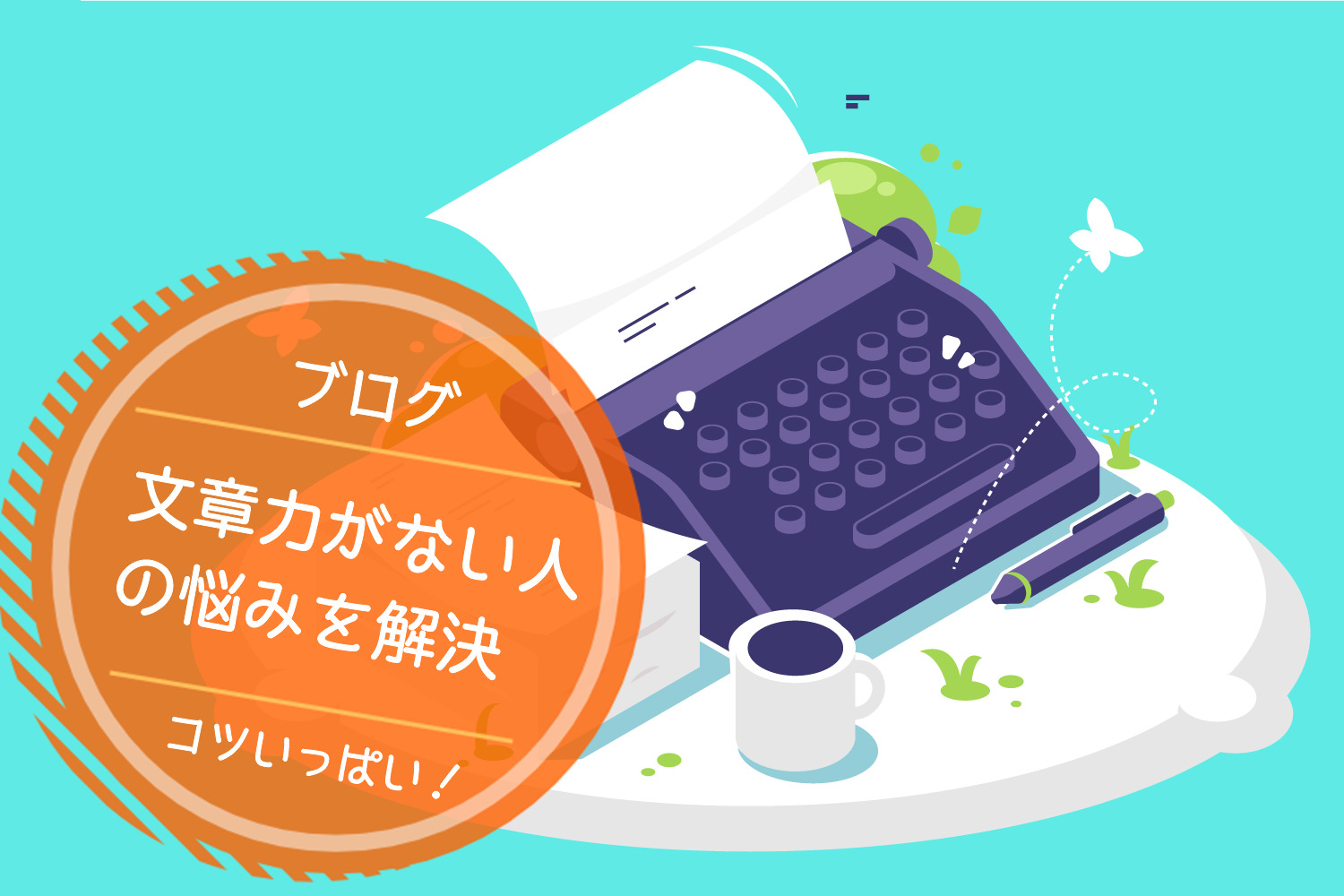・文章力が無いのでブログがうまく書けなくて悩んでいる
・上手な文章の書き方を教えてほしい
・ブログに必要な文章力アップのコツが知りたい
このような悩みを解決します。
この記事の内容
- ブログの文章力がない人が教科書にすべき「新しい文章力の教室」の紹介
- ブログの文章力がない人は、記事全体の構成を作っていない【構成は必須】
- ブログの文章力アップのために必ず注意すべき4点
- ブログの文章力がある人でもやりがちな3点
- ブログの文章力を補う記事作成のテクニッック
文章力がない人は、良い文章の基本的な書き方を学ぶ必要があります!
何事も基本が大事なのですが、学ぶのであれば文章のプロが書いたちゃんとした本から学ぶのが最善です。
なのでこの記事ではベストセラー新しい文章力の教室に書かれている内容をもとに良い文章を書くコツを解説していきます。
文章を書くど素人だった私も「新しい文章力の教室」を読んで、素人レベルから確実に文章力が上達しました。

ブログの文章力は小説のような特別なスキルを必要としませんが、基本の文章力はやはり必要です。
この記事の前半は、「新しい文章力の教室」をまとめた内容になっているので、文章力のない人はこの記事を読むだけでも書くコツがつかめます。
記事の後半では、ブログならではの文章のコツについて紹介します。
読みやすく分かりやすく書かれている文章の教科書のような本です。気になる人はチェックしてみてください。
ブログの文章力がない人が教科書にすべき「新しい文章力の教室」の紹介
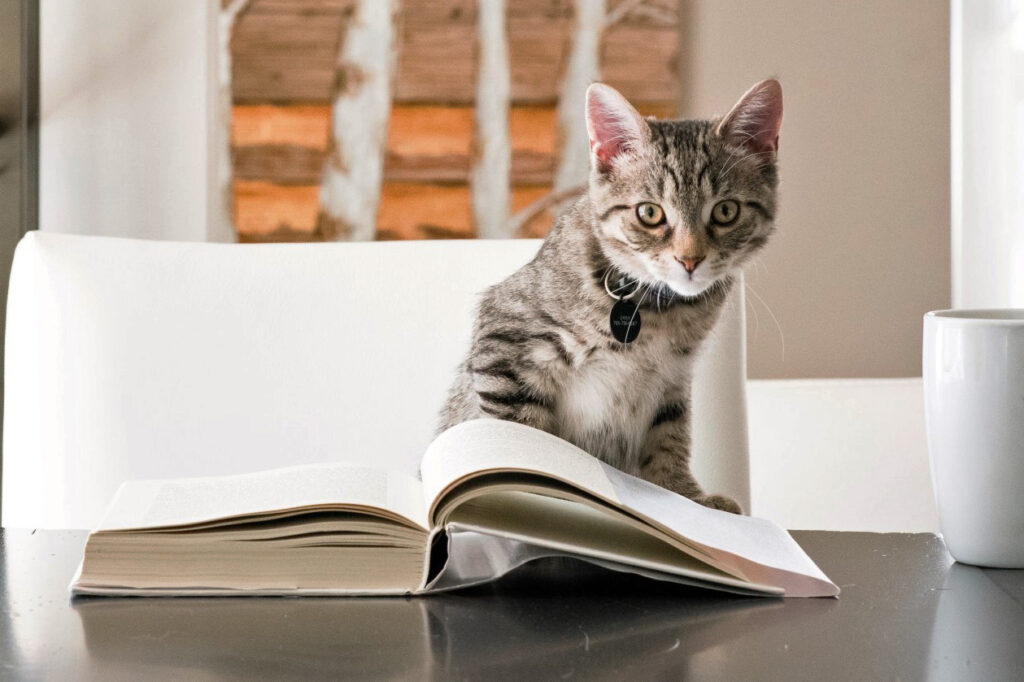
まず「新しい文章力の教室」の著者のプロフィールと本の概要をサクッとお話しします!
唐木 元プロフィール
- 大学在学中よりライターとして働き始め、雑誌・執筆・編集の現場に20年以上たずさわる
- ライブドアパブリッシング、幻冬舎、ジーノ編集部と3つの出版社に勤務
- 2008年、編集長としてニュースサイト「ナタリー」を立ち上げる
- 社内で新人ライター向けに「唐木ゼミ」と呼ばれるライティング教室を開催
大学時代からずっと文章に関わっているというか、文章に関わる仕事しかしてこられていないですね。
そんな唐木さんの経験に基づいた、良い文章の基礎についてたっぷりと書かれた本です。

小説の書き方や、個性的で目を引く書き方、論文の書き方など特定の分野については書かれていません。
化粧でいえば、マスカラやアイシャドーではなく、ベースメイクやスキンケアから教えていく必要があった。
「新しい文章力の教室」
と言っている通り、まずは文章を書く基礎を養いましょうという本です。
この本を読んで分かること
- 文章が苦手な人でも書けるようになる構造のつくり方
- 何を書くにしても活かせる良い文章の基本的書き方
- 読みにくい文章にありがちなポイント
- 読んでもらいやすい文章を書く手法
私は時間を置いて3回読み直したのですが、その都度「あ、そうだった!」と改めて気づかされます。

文章を書くときに初心者が特に意識すべきことを抜粋してまとめたので、このあとのポイントをぜひ参考にしてみてください!
ブログの文章力がない人は、記事全体の構成を作っていない【構成は必須】

この本では、「良い文章=完読される文章」と設定されています。
読みやすく、分かりやすく、飽きずに、違和感なく最後まで読める文章です。
文章力の乏しいブログにありがちなのは、記事の構成を作らずにいきなり文章を書いてしまっていることです。
なので、1番はじめに構成の必要性と作り方について説明したいと思います。
ラーメンで言うならおいしく完食できる一杯。その一杯を作るには準備が必要です。

書けない・止まる・つまる人は、あてのない散歩をしているよう
記事がうまく「書けない」の実情は、遅い・まとまらない・伝わらないのどれか。
書く前に準備をせず、いきなり書いているからです。
それはあて所のない外出のようなもので、どこへ向かうべきか判然としないまま歩き続けることになります。
「新しい文章力の教室」
風まかせではすぐに立ち行かなくなります。
具体的には、「テーマを決めて、何を、どの順番で、どれくらい」書くかを決めればスムーズに読みやすくなるということです。
簡単なのでぜひ記事を書く前にやりましょう!その作業を説明します!
3ステップで全体の構造ができあがる
ブログ記事を最後までスムーズに読ませるために、まず最初にゴールである目的地とそこまでの経路を決めます。
step
1書きたい話題を箇条書きで書き出す
今わかっている事実や、何を感じたかなど、箇条書きでリストアップしていきます。
step
2テーマを決めます
ブログ記事であれ、日記、プレゼン資料、報告書であれ文章で伝えるものには、テーマがないと何を言っているのか分からないからです。
書き出したトピックを見て、何について書くか必ず書き始める前に決めましょう。

step
3文章の骨子を立てます
テーマをうまく伝えられるように骨組みを固める作業です。
- 「要素=何を」… 最初に書き出した話題から、どれを書き入れるか選びます
- 「順番=どれから」… 書く順番を決めます
- 「軽重=どれくらい」… 重点度をABCの3段階でそれぞれのトピックを評価します
この3ステップをまとめると、
構造をつくる3ステップ
- トピックを箇条書きで書き出す
- トピックを見てテーマを決める
- 何を書くかチョイスし、順番を決め、重点度をABC評価する
初心者のうちは紙に書き出し、慣れてきたらPCやスマホのメモ帳などで行いましょう。
ブログ記事を書く前に下準備で構成を考えておけば、言いたいことが伝わる読みやすい記事ができます!
文章力アップのコツは、結論を文章の最初にもってくること【サビ頭】
文章の順番を決めるとき、伝えたい結論を文章の冒頭に持ってきてください。
最後まで読みたくなる結論や論点を初めにズバリ言って、読者の興味をグイッと惹きつけるのです。
これをJ-POPの用語で「サビ頭」と言います。
イントロの前に冒頭にいきなりサビをもってきて、聴者の興味を引く曲法です。

どういう話なのかわからない文章は、おしまいまで読まれる率が格段に下がります。
「新しい文章力の教室」
興味を引き、関心をキープしたまま、完読までこぎ付けるため、文章の最初に結論を持ってきましょう。
ブログの文章力アップのために必ず注意すべき4点

実は「新しい文章力の教室」には、約70個の文章の基本が紹介されています。
文章力がない人が特に意識した方がいいことを、初心者向けにまとめたので説明していきます。
その①:重複、くり返しをしないこと
同じ単語やフレーズがダブってないかチェックしましょう。
同じ言葉のくり返しは、読んでいてしつこく感じ、リズムが悪く、文法的にも誤りがあるなど、良い文章の邪魔になる要素です。
例
果物ではバナナが好きですが、大人になる以前ではバナナは好きではありませんでした。
例
朝早く起きたので、朝食前に散歩したかったので外出してみました。
上記の2つはどれも言い方を変えれば解消しますので、書き終えたらじっくり読んでみるのがいいですね。
例
会社で来季のミーティングをしました。参加者の意見がまとまらず紛糾しました。次は部長に入ってもらうことにしました。
まるで小学生の作文のようですが、意識しなければ意外とやってしまいます。
例
3月にロックフェスの開催が決定。場所は富士山も見える静岡のキャンプ場。海外のロックミュージシャンも出演。
体言止めの連続使用は、2連続するだけでもぶっきらぼうな印象を与えるので注意する箇所です。
重複は発生率が高いエラーなので、書き終えたら必ず読み返してチェックしましょう!

その②:主語と述語、修飾語と被修飾語のかみ合わせ
一文読んで違和感を感じる時は、主語と術後がうまくかみ合ってないことが多いです。
修飾語ではどの言葉を修飾しているのか分かりづらいこともしばしばです。
例
✖️ 彼女が「旅行に行くからお土産をかってくるね」と言ったので、楽しみにしています。
◯ 「旅行に行くからお土産をかってくるね」と彼女が言ったので、わたしは楽しみにしています。
✖️の文では、楽しみにしているのは「私」だけど、「彼女」が楽しみにしているとも読めてしまいますね。
主語と述語を近づけるのがコツです!
例
✖️ 貴重な80年前の保存状態がいい直筆原稿が発見された。
◯ 保存状態がいい80年前の貴重な直筆原稿が発見された
対応関係が複数あって一瞬では判読しづらい例です。
基本のコツは、主語と述語を近づける、修飾語と被修飾語を近づけることです。
文を分けて2文にスッキリさせるのもありです。

その③:短く、タイトに。初心者はだらだらと説明しがち
伝えたいことを、はっきりと率直に書く。
回りくどい説明を付けたり、柔らかい言い回しにしようと余計な表現を付けていませんか?
短くまとめるコツは、
- 接続詞を見かけたら、削れないかと疑う
「そして」「しかも」などは無くても通じるような文章にする - 「という」を削る
〇〇という食べ物。など - 強調しすぎな過剰な修飾語を削る
とてもキレイであまり目にすることのない珍しい石 → キレイで珍しい石 - 言い訳言葉はいらない
「お気に召さない方もいるかもしれないが」「あくまでも個人的な意見ということを伝えておきたいのだが」 - メタ言及的な言葉も余計である
「私の知る限りでは」「注目すべきは」「これから話すことは」「繰り返しになるが」
文章力のない人は自信がないからか、余計な表現をつけてそれっぽく書いてしまいがちです。
無意味に言葉を付け加えることなく、ストレートにタイトに言いたいことを伝えてください。
その④:誰でも理解できる言葉で具体的に
一般的にどんな人でも分かる言葉を使い、具体的な説明を心がけてください。
ブログは読者がいて成り立つので、だれが読んでも分かる文章表現にしないと伝わらないからです。
使わないように気をつける言葉は、
- 限られたコミュニティでしか通じない言葉
専門用語や業界用語、俗語、ネットスラングなど - ボンヤリとした抽象的な言葉
企画、作品、プロジェクト、物語、ストーリー、など - 「こそあど」言葉
これ、それ、あれ、この、あの、彼ら、など
楽をしようとすると自然と使っているので気をつけましょう!

あいまいな表現を避けて、具体的な言葉に変換しましょう。
ブログの文章力がある人でもやりがちな3点
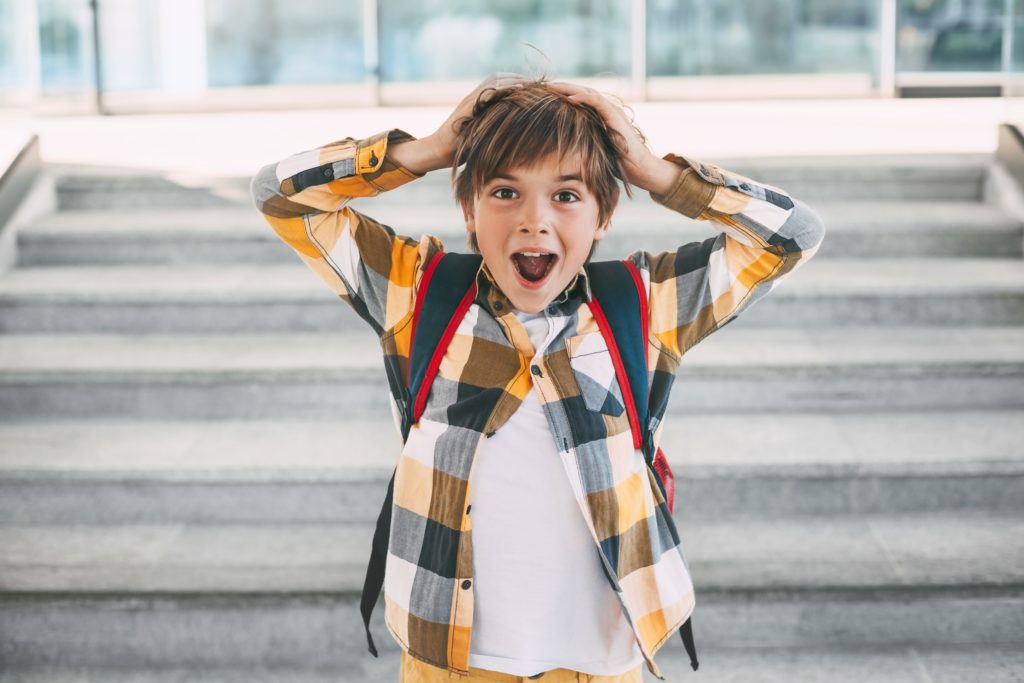
次の3つのテクニッックでさらに文章が上手になります。
指摘されないと文章力のある人でもやってしまいがちなのでチェックしてみてください。
その①:文頭の読点の位置に気をつける
一語目の直後に読点を打つと、すこし頭の悪そうな印象になってしまいます。
例
そして、私はいつもどおり学校に向かう準備をし始めた。
そして私は、いつもどおり学校に向かう準備をし始めた。
一語目の直後に読点を打たないほうが、スマートに感じられるコツです。
わたしはこの読点の打ち方にハッとしました。指摘されないとずっと最初に読点を打っていたと思います。

その②:「こと」「もの」を減らす努力をする
「こと」「もの」はとても便利な表現なので多用してしまいがちです!
- 理解することで → 理解すると
- 食べることは → 食事は
- 便利なものです → 便利です
「こと」「もの」は重複してくどくなりやすいので、適切な表現が思いつかないときに使いましょう。
初めのころのブログの文章を読み直したときに、「こと」「もの」をたくさん使っていたことにびっくりしました。

その③:漢字・ひらがな・カタカナの配分をバランスよく
漢字の使いすぎは読む人にむずかしい文章の印象を与えてしまいます。
逆に漢字が少なくひらがなばかりだと、文章の意味が理解しにくくなります。バランスが大切です。
- 漢字の使い過ぎ → 漢字の使いすぎ
- 繰り返し → くり返し
- 下さい → ください
- 先程の例は → 先ほどの例は
- 十倍に増加 → 10倍に増えた
- 極めて難しい → とてもむずかしい
- スマートなテクニック → スマートな技、上手なテクニック
- 膨大な時間と労力 → たくさんの時間とエネルギー
パソコンの変換に任せっきりだとどうしても漢字が多くなるので、「漢字・ひらがな・カタカナ」のバランスを意識しましょう!
ブログの文章力を補う記事作成のテクニック

これまでは文章を上手に書くコツについて「新しい文章力の教室」もとに説明してきました。
ここからはブログならではの見やすい、読みやすい記事の書き方を紹介します。
読みやすいブログ記事
- PREP法で文章を書く
- 並列概念はリストで説明する
- ボックスで囲ったり背景に色を付ける
1つずつ簡単に説明していきますね!
その①:PREP法で文章を書く
PREP法と呼ばれるライティング術を使えば、ど素人でも読みやすい文章が書けます。
なぜなら、ほとんどのブログ記事はPREP法を文章のテンプレートにして書かれているからです。
- Point:結論
- Reason:理由
- Example:具体例
- Point:結論
始めと終わりに結論を書くことがとても大切です。「サビ頭」ですね!
今あなたが読んでいる、この「その①:PREP法で文章を書く」という塊を見てください。
- Point(結論): PREP法と呼ばれるライティング術を使えば、ど素人でも読みやすい文章が書けます。
- Reason(理由): なぜなら、ほとんどのブログ記事はPREP法を文章のテンプレートにして書かれているからです。
- Example(具体例): まさに今この部分が具体例です!
- Point(結論): PREP法はブログの文章力がない人でも使える文章術なので常にこの型で書くように意識しましょう!
PREP法はブログの文章力がない人でも使える文章術なので常にこの型で書くように意識しましょう!←結論
その②:並列概念はリストで説明する
一列に言葉をならべて紹介するよりも、同じ概念のものはリスト化して説明しましょう。
見やすく工夫することは、読みやすさと理解のしやすさにつながるからです。
たとえば、「ブログ記事を書くときのポイント」を紹介するとき、横一列でずらっと書くよりも以下のようにリスト化した方が分かりやすいです。
- 記事の目的、テーマを決める
- 記事に何を書くかネタを書き出す
- どれを記事に書くか選ぶ
- 書く順番を決める
- 記事のタイトルを決める
- 一塊りの段落を全てPREP法で書いていく
- 音読してチェックする
というように、同じ概念のものを紹介する時はリストを使いましょう!
その③:ボックスで囲ったり背景に色を付ける
いくら文章力の高いブログ記事でも、文章だけで構成された記事は読みづらいものです。
記事を最後まで読んでもらうには、脳を疲れさせない、飽きさせない工夫が必要です。
こんな風にボックスで囲うとアクセントになります。
大事なことを伝えたい時などに使いましょう。
こんな風に吹き出しを使うことも読みやすくする工夫の1つです。

使い過ぎは逆にごちゃごちゃして見づらくなるので注意です!文字の色の多用も逆効果なので気をつけてくださいね!
まとめ:ブログの文章力がない人は基礎を身につけることから始める!

良い文章の書き方をまとめます!
構造をつくる3ステップ
いきなり書き始めず3ステップの下準備。
- 書く要素をリストアップする
- 要素を見てテーマを決める
- どれを書くか選んで、どの順で、どれだけ書くかを決める
文章を書くときのポイント
- 重複、くり返しをしないこと
- 主語と述語、修飾語と被修飾語のかみ合わせを分かりやすく
- 余計な表現をせず、短く、タイトに!
- ボンヤリワードを使わず、具体的な言葉で
- 文頭の読点の位置に気をつける
- 「こと」「もの」を減らす努力をする
- 漢字・ひらがな・カタカナをバランスよく
新しい文章力の教室にはもっとたくさん紹介されていますが、初心者向けにこれだけはというポイントをピックアップしてまとめました。
ブログの文章力を鍛えるには、良い文章の基礎力をつけることがまず大切です。

文章の基本を知ったら、ブログ記事をPREP法で全ての塊を書いてみましょう!書くことがトレーニングです笑
文章力の秘訣をもっと知りたい人はぜひ一度読んでみてくださいね。