PREP法って本当に必要?ブログでは逆効果になるケースもあります
今日は「ライティングの型」について、ちょっと話したいと思います。
PREP法で書かないとダメ?という思い込み
よく聞きますよね、「PREP法で書きましょう!」って。
文章の書き方をGoogle検索したり、YouTubeでブログノウハウ見たりすると、ほぼ確実にPREP法が出てきます。
でも、先に言っておきますね。
僕、ブログ記事をPREP法で書いてません。
PREP法って、
●Point(結論)
●Reason(理由)
●Example(例)
●Point(もう一度結論)
ってやつです。
「ブログ初心者はまずPREP法から」っていう情報、よく見かけます。
でも、これって無料ノウハウ界隈では定番っぽく扱われてる話なんですよね。
実際、僕は今まで有料のブログ教材、情報商材、添削サービス、コンサル、いろいろ買ってきましたけど…、PREP法で書くことを強く勧めている教材やサービスってほとんど無いです。
紹介されている場合はありますけど、登場すらしないこともあります。
ネットで「ブログ記事 書き方」って検索すると、まぁだいたいPREP法が出てきますよね。
もちろん、この型が便利な場面もあるのは分かってます。
でもね、「なんでもかんでもPREP法で書け」っていう風潮、ちょっと違うんじゃない?って思うんです。
もちろん使える場面はあるけど、ブログ記事の“全部”にPREP法を当てはめる必要は一切ありません。
僕が採用している「結論 → 自由 → 結論」の型
僕が普段やってる書き方は、超シンプルです。
結論 → 自由に書く → 結論。
これだけ。
PREP法みたいなガチガチの型じゃなくても、十分伝わるし、むしろ読みやすくなることの方が多いんですよ。
ブログ記事の各見出しも、この「結論・自由・結論」の流れで書けばOK。
読者にとって必要なことだけシンプルに届けられれば、それでいいと思ってます。
でも、ネットで検索すると、「PREPが分かりやすい」とか、みんな言ってます。
正直、僕も昔はそれを信じてました。
PREP法=正解だと思ってたし、「検索上位にある記事を真似すればいい」って思ってました。
でも、今は違います。
それはなぜかというと、PREP法には「使える場面」と「使えない場面」があるから。
たとえば、
「大谷翔平のお母さんの名前は?」
「この商品はドンキで売ってるのか?」
こういうトレンド記事とか、調べ物系の記事で、いちいちPREP法を使ってたら、読者がイライラします。笑
お母さんの名前を伝えるのに、PREP法のExampleである「たとえば」を語る意味…ないですよね。
ドンキで売ってるかどうかも、「売ってる/売ってない」を即答すればいいだけ。
しかもPREP法を全見出しに当てはめようとすると、「Example」の部分、具体例がとにかくしつこくなる。
PREP法って、実は“読みやすい”ように見えて、過剰に使うと読みづらくなるという落とし穴があるんです。
なので僕は、PREP法を見出し単位で多用するのはナシ派です。
ジャンルやテーマ次第では、まったく不要だと思っています。
僕が普段やってる方法は先ほどお伝えしたようにめちゃくちゃシンプルです。
●結論
●間は自由
●最後にまた結論
これだけ。
つまり、「PREPのフリースタイル版」みたいな感じ。
この「結論→自由→結論」構成が、どんなジャンルでもほぼ対応できて、書くのもラク・読まれる・伝わるという三拍子。
しかも、「例え」や「理由」も必要に応じてだけ挟めばいい。
自由度が高くて、汎用性もあって、読みやすさもちゃんと担保できる。
PREP法は初心者にとっての“型”としては優秀。
でも、その型に縛られていたら、逆に記事が書きにくいこともよくあります。
で、これが一番言いたいことなんですが…
PREP法って「分かりやすくするための手段」であって、「目的」じゃない。
文章の目的って、
- 読者に伝えること
- 行動してもらうこと
- 信頼を得ること
であって、PREP法で書くことじゃないですよね?
なので、型を使おうと一生懸命になる必要なんてありません。
PREP法が向いている記事と向いていない記事
「じゃあPREP法っていらないの?」
いや、使いどころを見極めれば全然アリです。
たとえば、商品紹介とかレビュー記事とか、ちょっと説得力を出したい場面。
この商品おすすめです
→ なぜなら…
→ 例えばこういう機能が
→ だからおすすめです
これはPREP法、めっちゃハマります。
でも、
「茅野だし どこで売ってる」
「40代 女性 授業参観 服装」
なんて記事では、ほとんどの見出しでPREP法は不要。
使い分け、これが大事ってこと。
なので、
「結論 → 自由に書く → 最後にもう一回結論」
この流れをベースにしつつ、PREP法は必要なときだけスパイス的に使うくらいがちょうどいいんじゃないかと思ってます。
ブログもメルマガも「伝わる構成」が最優先
今回のメルマガも、最初に「PREP法を全部で使わなくていい」と伝えて、最後にもう一度、同じことを結論として書いただけ。
その間の文章は思っていることを自由に書きました。
これってメルマガだからできるわけではなくて、ブログ記事の各見出しでも同じようにできます。
結論をしっかり伝えることを意識するだけでも、読者にとってはすごく読みやすくなります。
僕がやっている書き方であれば、自由度が高くて万能ですし、伝えたいことはちゃんと伝えられるし、型ばかりの文章で硬くなりすぎたりしつこくなってしまう恐れもありません。
読者が「読みやすい」と感じる文章って、決して“教科書的”じゃないんです。
むしろ、“ちょっと崩してる”くらいがちょうどいい。
僕も無料情報を漁っていた初心者の頃はPREP法信者でしたけどね。笑
ということで、今回は「ライティングの型に縛られすぎないでね!」というお話でした。
感想とかあれば、返信で気軽にどうぞ!
それではまた、次回のメルマガで☆
あとがき
この話をしようと思ったのは、先日プレゼントした『少ない記事数でも収益化する方法』の無料レポートがきっかけです。
結局あれは15,000文字超えのなかなかボリュームある内容だったんですが…
「スラスラ読めた」とか「一気に最後まで読めた」という感想を何人もいただいたんですよね。
だから今回伝えたいのは、ブログの記事やレポートなどを書く場合は、「もっとシンプルな書き方でいいんですよ」ってことです。
PREP法は、使ってもいいし、使わなくてもいい。
使い方次第ではとても説得力が出るけど、間違えると読みづらくなることもあります。
だったら、伝えるべきことを最初と最後に“結論”としてしっかり押さえて、その間を自由に、自分の言葉でつないであげる。
それだけで、ちゃんと伝わるし、
読みやすい文章になる。
「正しく書く」よりも、「伝わるように書く」を意識してみてるといいかなと思います(^^
「この文章、ちゃんと伝わるかな?」
「これ、意味分かるかな?」
ってことを自問しながら文章を書いてみるのもおすすめです。
とはいえ、今はAIがありますからね!
AIに添削してもらったら、自分で書くよりも分かりやすくなっちゃう、なんてことよくあります。笑
文章に自信が無い場合はAIを使いましょう!
…って、最後に元も子もないあとがきになってしまいました。笑
【プレゼント】迷子だった僕がたどり着いた答え、それは…
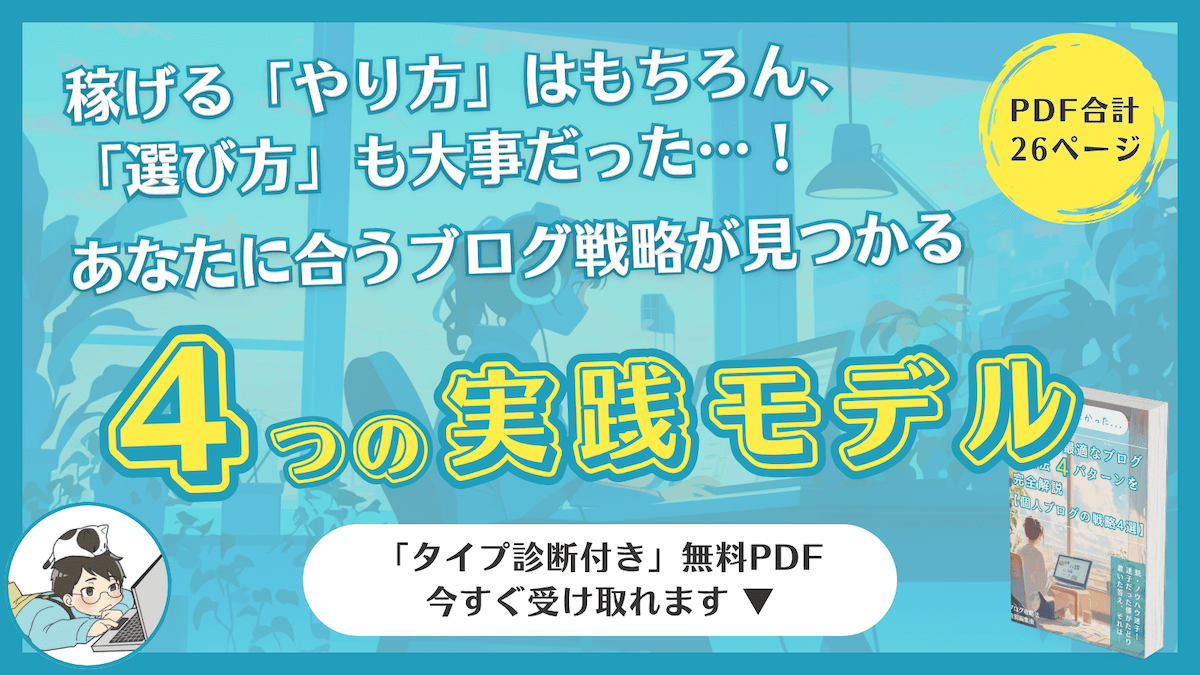
ここまで読んでくれたあなたは、きっとすでに「行動してる人」だと思います。
教材を読んだり、記事を書いたり、ときには不安になりながらも一歩ずつ進んできたはず。
でも、
「頑張ってるのに突き抜けた成果が出ない。」
「やり方は間違っていないはずなのに、結果がついてこない。」
「このまま進んでて大丈夫なのかな…」
そんなモヤモヤを感じていませんか?
僕も、最初はそうでした。
思ったようにブログで稼げずノウハウばかり集めていましたし、「自分に合う戦略」が分からなくて、結局、遠回りしてしまってたんです。
稼げる「やり方」はもちろん大切ですが、「選び方」も大事だと後から気づきました。
だからこのレポートでは、僕が本気で「もっと早く知りたかった!」と思った、ブログ戦略の「選び方」をギュッとまとめました。
- 迷って止まる前に
- ムダに遠回りして消耗する前に
この1冊のレポートが、あなたの「次の一歩」になるかもしれません。
今だけ無料で配布していますので、よかったらぜひチェックしてみてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!